一酸化炭素の基本!二酸化炭素との違いや工場におけるリスク管理方法を解説
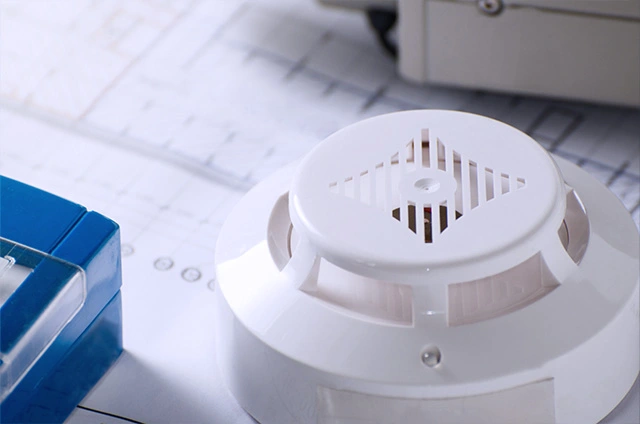
一酸化炭素は、工場や作業現場で発生する重大な有害ガスです。無色・無臭で気づきにくく、知らないうちに従業員が被ばくすれば、重篤な健康被害や死亡事故につながるおそれがあります。
万が一、事故が発生し、使用設備の管理不備や安全教育の不足が原因となれば、企業や経営者が法的責任を問われるリスクも高まります。労働安全衛生法や関連法規への遵守はもちろん、安全教育や職場環境整備に取り組むことは、経営者として最重要課題の1つといえます。
そこで、一酸化炭素の基礎知識と二酸化炭素との違い、そして工場における具体的なリスクとその対策について、経営の視点からわかりやすく解説します。
目次
一酸化炭素とは
一酸化炭素(CO)は、匂いや色、味もない、とても危険なガスです。燃料が不完全に燃えたときに発生し、衣類乾燥機や給湯器、暖炉、ガスコンロ、自動車、バーベキュー用のグリル、発電機、薪ストーブなどからも出ることがあります。このガスを吸い込むと、体の中の酸素が奪われ、頭痛やめまい、吐き気、意識がもうろうとするなどの症状が出ます。ひどい場合は、意識を失い、命を落とす危険もあります。
一酸化炭素は五感では気づくことができないため、「静かな殺し屋(サイレントキラー)」とも呼ばれています。こうした事故を防ぐには、一酸化炭素警報器を設置するなどの対策を施す必要があります。また、燃料を使う機器は毎年専門の業者に点検してもらい、十分な換気を心がけてください。
関連ページ:一酸化二窒素とは?産業発展で活躍する半面環境や健康リスクあり
二酸化炭素との違い
一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO₂)は、どちらも色や匂いのないガスですが、性質や体への影響は大きく異なります。まず、化学的な違いとして、一酸化炭素は「C+O」という元素でできている一方、二酸化炭素は「O+C+O」でできています。
一酸化炭素は、ストーブやエンジンなどで燃料がきちんと燃えなかったとき(=不完全燃焼)に発生します。自然の空気中にはほとんど含まれていませんが、体にとっては危険なガスといえます。というのも、体の中の酸素を運ぶ働きをじゃましてしまい、少しの量でも頭痛やめまい、吐き気などの症状が出るからです。量が多いと、意識を失い、場合によっては命にかかわることもあります。
二酸化炭素は人の呼吸や植物の分解、火山活動など、自然の中でよく見られるガスで、空気中に約0.04%存在しています。普通の量であれば体に害はありませんが、非常に高い濃度になると、酸素が足りなくなり、窒息の危険が出てきます。
また、一酸化炭素は燃える性質がありますが、二酸化炭素は燃えません。このように、見た目ではまったく分からない2つのガスですが、性質やリスクはまったく違います。
関連ページ:地球温暖化はなぜ起こる?温暖化の原因と影響を解説
空気との重さの違い
一酸化炭素は、空気とほとんど同じ重さのガスです。正確には、空気より少しだけ軽いです。そのため、一酸化炭素が発生すると、空気の中にすぐに混ざり、部屋の中で特定の場所(たとえば低い所)にたまるというよりも、広い範囲にふわっと広がる性質があります。この性質から、警報器を設置する場合は、なるべく部屋の高い位置に取り付けるのが効果的です。
工場での一酸化炭素使用リスクと対応フロー
工場で一酸化炭素がもたらすリスクは、とても深刻です。一酸化炭素は、色も匂いもないため、人の感覚では気づけない有毒なガスだからです。このガスは、プロパンやガソリンを使うフォークリフト、ガスオーブン、発電機、溶接機、自動車の排気ガスなどが原因で発生します。
頭痛やめまい、吐き気、意識がもうろうとするなどの症状が出ますが、こうしたリスクを防ぐために、どのように対応すればよいか詳しく解説します。
重大な事故になった場合
工場でガスオーブンや給湯器、暖炉などの燃料を使う機器や、フォークリフト・発電機・溶接機・自動車などの内燃機関を使う際には、不完全燃焼によって一酸化炭素が発生するリスクがあります。一酸化炭素は、匂いもないため気づきにくく、気づいたときには症状が出ていることも多いため、重大な事故につながる可能性があります。
そのため、従業員には、一酸化炭素中毒の原因や症状、予防方法について、しっかりと教育しておく必要があります。もし中毒が疑われる重大事故が起きた場合は、まずは症状が出ている人をすぐに新鮮な空気のある場所へ移動させ、速やかに救急(119番)へ連絡してください。そして、安全が確認されるまでは誰も現場に立ち入らないようにし、原因の特定を急ぐようにします。
事業継続リスクにつながった場合
事故が発生した場合、企業は労働安全衛生に関する法的責任を問われるだけでなく、企業の社会的責任や事業の継続にも深刻なリスクを及ぼす可能性があります。
こういったリスクを防ぐには、一酸化炭素が発生した原因を突き止め、関係する機器の使用を止めたうえで、専門業者に調査や点検、修理を依頼します。再発を防ぐために、換気設備や警報器の設置状況をもう一度見直し、従業員への教育や訓練の計画も必要に応じて検討してください。
そして、今回の被害状況や対応について、社内はもちろん、取引先や関係者にも報告し、企業としての信頼を取り戻すよう努めてください。
一酸化炭素のリスク管理方法
ガスは目に見えず、匂いもないため、気づかぬうちに体内に取り込まれ、健康被害を引き起こすことがあります。特に工場では、不完全燃焼による発生リスクが高く、対策が不十分だと重大事故につながるリスクがあります。そこで、換気や警報器の設置、安全教育など、具体的なリスク管理方法について解説します。
十分な換気がされているか管理する
一酸化炭素による中毒事故を防ぐためには、換気がされているかどうかを管理することが基本です。もし換気が不十分な空間で、このガスが発生すると、短時間のうちに濃度が上がり、室内にいる多くの人に重大な健康被害を与える可能性があります。
また、このガスは空気とほぼ同じ重さのため、部屋の一部にとどまるのではなく、空間全体に広がる性質があります。そのため、特定の場所だけ換気すればよいわけではなく、工場全体に換気システムを整備し、それを常に稼働させておくようにします。
ただし、換気だけでは安心とは言えません。見た目やにおいで気づけない一酸化炭素を確実に検知するためには、空気中の濃度を定期的に測定する取り組みなど、他の方法と併せて対策をとるようにしてください。
警報機や測定器を設置する
工場で一酸化炭素による中毒事故を防ぐためには、警報器や測定器を設置することも大切です。工場では、作業員が身につけて使える個人用のCOモニターを配布することが推奨されています。また、建物全体に固定式のCO検出器を設置し、定期的に空気中のCO濃度を測定することも必須といえます。
注意しなければならないのは、CO用の検出器と、CO₂用の検出器は、それぞれ異なるセンサーを使っているため、代用はできないという点です。そのため、用途に合った正しい機器を選ぶようにしてください。また、警報器がいざというときに確実に働くよう、定期的な点検とバッテリー交換を忘れずにおこなうようにします。
安全教育を徹底する
工場で中毒事故を防ぐには、安全教育を徹底することが重要です。安全教育は従業員に対してだけでなく、工場を訪れる取引先や来客も含めて、CO中毒の危険性や発生しやすい場所、症状などを正しく伝えておくのが望ましいです。
中毒の症状としては、頭痛やめまい、吐き気などがあり、インフルエンザのような症状にも似ているため、病気によるものだと誤解されることもあります。
特に、「工場から離れると体調が良くなる」「屋内で作業中にだけ体調が悪くなる」といった場合は、中毒の可能性を疑うようにしてください。こうした教育は、一人ひとりの命を守るために欠かせない取り組みです。管理職や経営層は、安全教育を継続的に行い、現場に根づかせていくよう努力してください。
まとめ
一酸化炭素による事故を防ぐには、その性質を正しく理解し、日常的な管理と万が一の対応フローを確認しておくことが大切です。特に工場のように普段から燃料を使う機器が多い環境では、換気や警報器の設置、安全教育など、複数の対策を組み合わせることで初めて安全が確保されます。見えない危険だからこそ、日々の管理が大切で、従業員や関係者と一緒になって取り組むようにしてください。
関連サービス:省エネ/排熱回収コンサルティング

